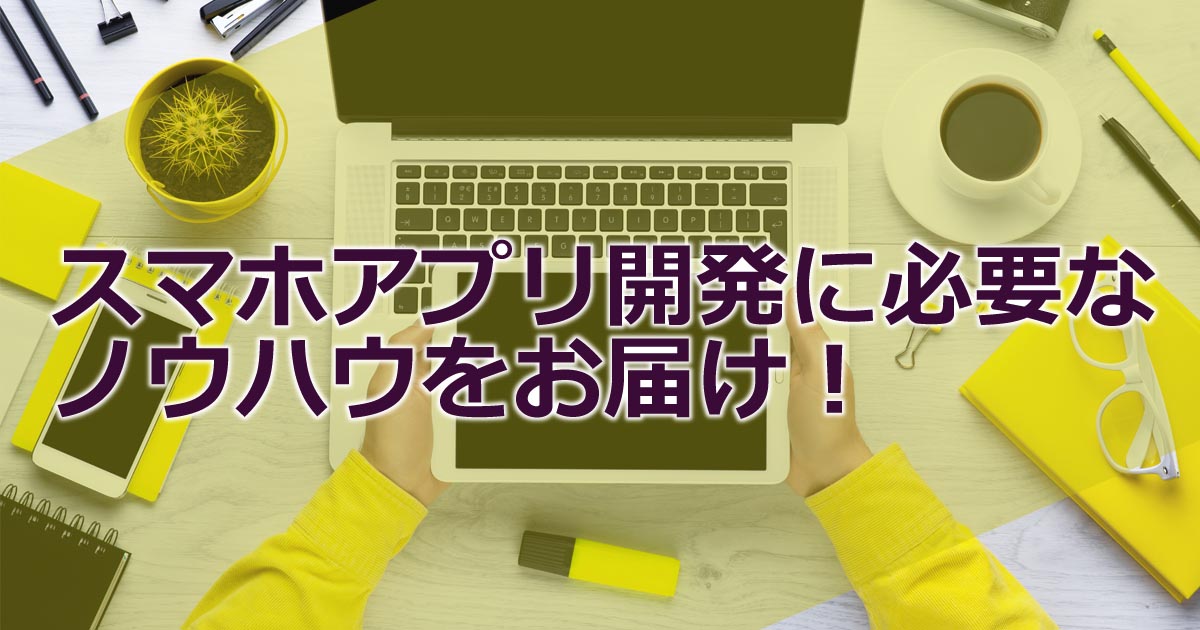CXデザインにおけるBMLモデル:真の顧客中心思考とは

顧客体験(CX)のキーワードは、PDCAからBMLモデルに変わりつつあります。
単一の正解がなく、検討すべき要因が多いデジタルマーケティングにおいて、CXの最適な施策を講じるとはどのようなことなのでしょうか。
本記事では、CXのそもそもの意味と、BMLモデルについて重要視する項目を具体的に挙げながらご紹介します。
【目次】
- 顧客と企業のタッチポイントのキーは顧客体験「CX」
- 日本はCX後進国なのか
- BMLサイクルとは
- BMLサイクルでCXを改善
- バリューチェーンからバリュージャーニーへ
- BMLサイクルにとってのポイントPWAとは
顧客と企業のタッチポイントのキーは顧客体験「CX」
従来の顧客体験(カスタマーエクスペリエンス:CX)といえば、PDCAがキーワードでした。
そもそもCXは、企業の開発姿勢や取り組みを顧客最優先でおこなうという理念のことです。
企画から実行し、その結果を検証、検証した分析を反映して修正、このサイクルがマーケティングの最小PDCAサイクルといわれており、CXにおいてもこのサイクルをうまく回していくことが重要と考えられていました。
しかし、現在はPDCAサイクルからの脱却する動きが高まっており、「BMLサイクル」に変わりつつあります。
日本はCX後進国なのか
オリンピック開催国に決定したことで「おもてなし」という言葉が流行しましたが、日本企業はCXの重要性を理解していながらもCXの最適化については遅れをとっているという見方があります。
多くの日本企業が考えるCXは、クリエイティブな領域の仕事であり、改善活動の一部。現場レベルの取り組みで完結してしまっていることが多いとされています。
本来のCXは企業理念であり、ただ単に顧客をおもてなししたり、ブランドメッセージを発信し続けるだけのものではありません。また、「理念」のため本来であればトップから現場まで共通の認識として浸透している必要があるのです。
米国家電量販店はCX重視のデジタル改革で回復
米国の家電量販店BEST BUYは、CXを重視したデジタルマーケティングによってV字回復を成し遂げました。
カスタマージャーニーの規定、その過程に生じるタッチポイントにおける顧客体験データの蓄積、分析によってさまざまな施策を講じました。
顧客プロファイルは既存顧客、潜在顧客を問わずに単一IDで管理され、1万2,000の属性からその人に最適なレコメンドされるようにシステム化されました。
結果として、専門家も驚きの回復をみせています。CXに基づいた施策が、停滞する経営状況を回復させ、オンライン/オフライン両方での復調を実現したのです。もっともBEST BUYの事例は特別なものではなく、米国企業の多くはCXの重要性をひとつの前提ととらえています。その多くの取り組みにおいてCXの定義は語られていません。
これは裏を返せば、日本企業がCXを軽視したり本来の理念を取り違えたまま対策をとったりすると、順調であった状況が一変するかもしれないということでもあります。
・BEST BUY
https://www.bestbuy.com/

BMLモデルとは
BMLモデルは、リーンスタートアップのプロセスである「Build(構築)、Measure(計測)、Learn(学習)」の頭文字をとったもので「定量的に測定するループを繰り返す方法論」です。
BMLモデルをCXデザインに活用する場合は、以下のサイクルを回す必要があります。
- Build……顧客体験の構築・提供
- Measure……顧客体験の計測
- Learn……顧客の理解
望ましい顧客体験を提供するための施策をプランニングし、それを実施、顧客の実際の行動や心理の変化を計測してデータ化し、対象である顧客の心理やあり方といったものの変容の仮説をモデル化(定義づけ)するプロセスを意味します。
これまでのPDCAは、いわば効率主義であり、これからは真に顧客中心であるBMLへのシフトが求められます。PDCAは「品質」や「効率」といった単一の正解を目指すサイクルでしたが、BMLモデルは「顧客中心」という正解のない最適化アプローチの方法です。つまり、次のデジタルマーケティングにおいて求められているのは、唯一絶対の回答がないものということになるでしょう。
PVや直帰率、会員数といった数字を実績や指標として示す時代は終わりを告げようとしています。
BMLは、
- 顧客の認知度や期待度がどのようなものか
- 顧客がどのような状態でサイトを訪れているか
- サイトを訪れてどのような行動をしたか
- サイト閲覧を通じて顧客の心理や行動がどのように変容したか
という数字にあらわれてこない部分を指標化する必要があります。
BMLサイクルでCXを改善
では、具体的にBMLサイクルでCXを改善する方法について考えてみましょう。
各フェーズでどのようなことをするかイメージを明確にすることで、真のCXを実現できます。
BUILD:顧客体験モデルを構築
顧客体験モデルを構築するためには、まず顧客を理解する必要があります。カスタマージャーニーマップ(CJM)の作成、シナリオ作りによって顧客体験をモデリングし、提供のための商品開発やマーケティング施策を講じていきます。
現代の多くの顧客体験は、利便性と感動(CD/カスタマーディライト)のどちらかに目標を設定することで成功しています。
つまり、顧客がストレスなく買い物ができる、サービスを享受できる状態が利便性を追求した顧客体験であり、そこでしかできない特別な体験や類似サービスよりも抜きん出た最高のサービスは感動を追求した顧客体験といえます。
こうした目標に沿ってモデル化された顧客体験は、広報によって実際の顧客まで情報が届けられ、提供されます。
スマホの普及によってSNSをはじめとしたさまざまなツールがマーケティングに活かせるようになり、顧客接点は増えています。しかし一方で、広告の回数が過剰だったり一貫性がなかったりすると、カスタマーが商品に対してネガティブなイメージをもつリスクも発生しています。
これを防ぐのが顧客体験モデルの設定で、つまりはモデル化することで商品開発からオンライン、オフラインを含むマーケティングにいたるまでの一貫性を保つ役割を果たすことになります。
MEASURE:顧客体験からデータを計測
実際に顧客に商品やサービスが提供されたら、その顧客体験を計測します。
顧客体験は、行動や心理、また顧客の属性といった数多くのデータを取得することができます。これらのデータを統合し、さまざまな組み合わせで分析することによって顧客がプロファイリングされ、次の商品開発やマーケティング施策に活用されることになります。
顧客体験の計測にあたっては、AIを役立てる場面があるかもしれません。従来にはなかった視点での分析方法を導入することによって、まったく新しい施策が見えてくる可能性があるからです。
Adobeは、魅力的な顧客体験の創出には、感情データの活用が欠けているとしています。
感情データは顧客心理データとも称されます。これは、各チャネル間で収集されたデータのギャップを埋める情報になると目されているデータでもあり、AIにこのデータを与えることでより効果的にマーケティングやキャンペーンをおこなえるとされています。
具体的な収集方法としては、顔認識技術の活用や、ウェアラブル端末によるバイオフィードデータの取得が挙げられています。
Adobeはまた、心に残る感情を生成する顧客体験は、提供企業への親の感情を芽生えさせるとしています。企業への親しみは顧客の選択に影響を与え、売上や顧客の可処分時間の獲得につながっていくでしょう。また、こうしたデータの計測は、新たな商品やサービス開発にも大いに役立つものです。
LEARN:顧客データから学ぶ
計測した顧客データは、企業にとっての次の開発方向性を示す暗号や地図のようなものといえるかもしれません。
たとえばあるECサイトでは、ユーザーは以下のようなプロセスを経てリピーターへ定着すると定義します。
- 期待
- 検討
- 初回購入
- 活用
- 定着
流入チャネルごとに、これらに対して短期的評価、長期的影響をおこないデータ分析を実施します。
なお、これらのデータ分析においても単に数字のみを比較検討するのではなく、顧客それぞれの心理状態を考慮すべきデータとして定義することが重要になります。
前のフェーズでも繰り返しふれた内容ですが、この「心理状態」の計測と分析こそが顧客体験モデルの構築と、真の顧客中心主義の要といっても過言ではありません。
心理データは、顔認識技術やバイオフィードのデータ取得といった新しいテクノロジーと、膨大なデータを処理して有用な顧客データとして蓄積できるAIがあってこそ「データ」として活かせるものです。デジタルが当たり前に存在するようになった現代ならではのビジネス手法といえるでしょう。
BMLモデル(顧客理解)に役立つデータ
BMLモデルに役立つレポートには、次のようなものが挙げられます。
- リアルチャネルの売上データ
- Web上のデータ
- アンケートによる顧客満足度調査(定量と定性)
これらのデータを、行動・属性・心理など分析するために活用し、総合して顧客理解を深める努力をすることが重要です。
バリューチェーンからバリュージャーニーへ
顧客中心主義とそれにともなうBMLモデルの確立、つまりアフターデジタルの時代に沿ったビジネスは、バリューチェーンからバリュージャーニーへとその方向性を定めています。
これまでのビジネスは、大量生産した商品を販売マーケティングのプロセスに落とし込んで売るという、顧客ではなくプロダクトが中心となる展開方法をとってきました。このバリューチェーンにおいて、顧客体験はその商品単一のものにとどまり、次の商品開発やマーケティングにつなげることができません。
一方のバリュージャーニーは、顧客に長期間寄り添ってデータを取得していくやり方です。継続的な価値提供をおこなうことによって顧客接点や顧客データを多く取得し、それらを分析して得た情報を新しい顧客体験へと還元していくこのやり方なら、顧客体験は単一のものにはなりません。
製品、デジタル接点、店舗接点、リアル接点など多くの点を線で結び、顧客体験の改善や進化をうながしていくプロセスが、バリュージャーニーです。改善によってよりよい体験を提供することで、顧客は離れることなく継続的に製品やサービスを利用するようになり、その分だけデータも溜まっていきます。結果として、点のみだったバリューチェーンよりも多くの可能性と展開が発生していくことになります。
BMLモデルにとってのポイントPWAとは
スマホでECにつながる顧客が増加し続ける昨今、モバイルファーストにどのように対応していくかという点は非常に重要です。
先に挙げたPWA(Progressive Web Apps)は、モバイルファーストを実現する1つの要素として、併せて知っておきたいキーワードといえるでしょう。
PWAは、GoogleがWebとモバイルのギャップを埋めることを念頭に置いて提唱しているもので、同社はPWAとして次のような4つの要件を掲げています。
- ユーザーが5分以上間隔を空けて2回訪れるか
- HTTPS化をサポートしているか
- 有効なJSONのマニフェストが含まれているか
- Service Workerが含まれているか
この要件を満たしさえすれば、自由にカスタマイズすることができます。
PWAは、アプリストアを経由しないため登録審査などが不要であり、それでいてアプリのようにプッシュ通知機能を使えたり、ホーム画面に追加できたりと、既存のWebサイトよりもさらにユーザーに近い形での運用が可能になります。
フルスクリーン表示なども可能で、ブラウザを起動しなくても該当サイトが開けるため、操作性も高くなります。
検索やブックマーク一覧からチョイスすることなく開けるPWAは、CXデザインを考慮する上で、検討材料のひとつとなることでしょう。
一方で、開発に時間がかかる、モバイルのみでしかリリースできないためWebからのユーザーを除外することにもつながりかねない、といったデメリットもあり、慎重に検討する必要があります。
まとめ
真の顧客中心的な姿勢とは、企業やサービスの数だけ正解があります。
これまでの数字を絶対の根拠として施策を講じるやり方からは、180度思考が変わると感じる企業トップも多いかもしれません。
社内での意識共有や、データの効果的な分析方法について、再考することでこれからのCXデザインがみえてくるのではないでしょうか。
PR:エスキュービズムによるDX推進アプローチ