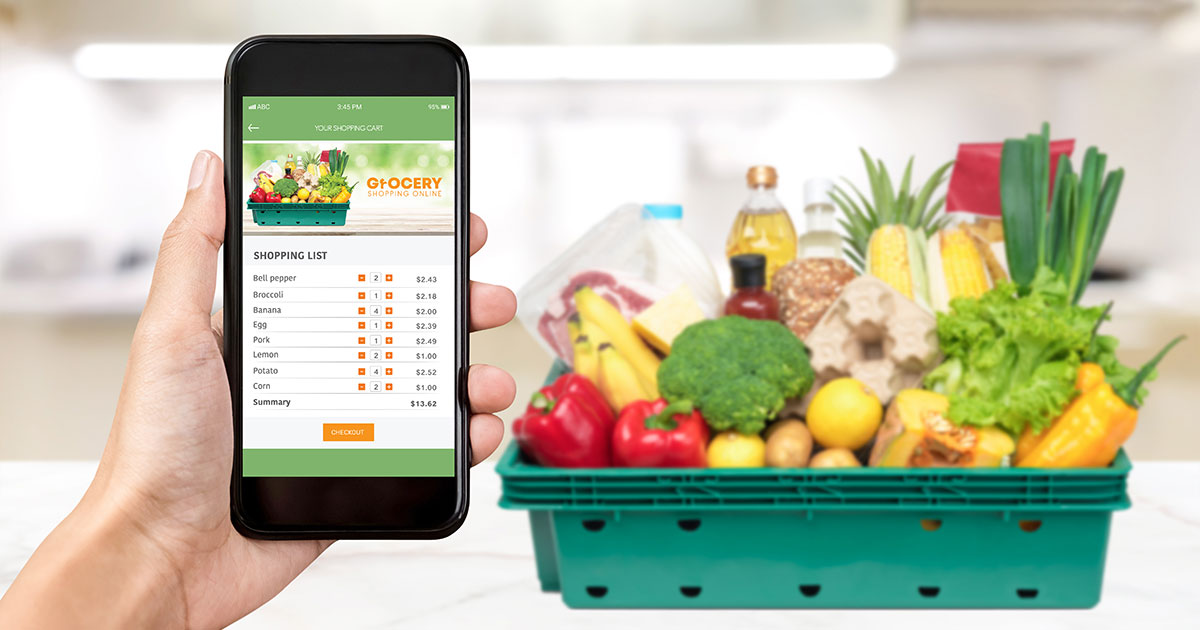これからのOMOはバリューチェーンからバリュージャーニーへ

2019年7月24日~25日に開催された日経クロストレンド FORUM 2019にて、株式会社ビービットの執行役員/エバンジェリストの宮坂 祐 氏が講演を行いました。
ビービット社といえば、日経BP社から2019年3月に出版された「アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る」を執筆した藤井保文氏が所属するコンサルティング企業。同著はAmazonのビジネスカテゴリーで1位になるなど、2019年上半期の話題をさらいました。
本記事では「『アフターデジタル』~OMO‐UX戦略と日本型DXの在り方」と題した講演をもとに、OMOやDXについて考えてみようと思います。
【目次】
- スマホ以降の「アフターデジタル」とは
- モバイクの事例にみる「新しいビジネスヒエラルキー」
- これからの企業に重要なOMOの考え方
- バリューチェーンからバリュージャーニーへ
- あるべきDX(デジタルトランスフォーメーション)の姿
- UXデータサイクルを実行するためにはデジタル人材育成がカギ
スマホ以降の「アフターデジタル」とは
ここ数年で独自のテクノロジーと独自のサービス、UX提供で話題になることの多い中国。
ビービット社では中国の拠点を通じて、独自サービスの充実は「日本を超える部分がでてきている」と実感しているといいます。
1908年にフォードが自動車を発売してから5年で、ニューヨークの移動手段が馬車から自動車に置き換わったように、紙媒体としての新聞の発行部数が下がり、電子版の契約数が上がってきています。また、音楽もレコードからテープ、CD、そしてデータ配信へと媒体を移行するなど、スマホなどのモバイル端末の普及がパラダイムシフトを引き起こした結果、従来のマーケティング概念や手法にも変革を求められるようになってきました。
現在、平均的な日本人のスマホユーザーは「1日3時間、150回」スマホを見ているといいます。2007年にアップルが初代iPhoneを発売してから12年で、「スマホのない生活」が考えられなくなってきています。
スマホが出る前をビフォアデジタル、スマホが出た後をアフターデジタルと称し、宮坂氏は「リアルワールドの中にオンラインが内包されており、実質的にオフラインがなくなっている状態」になっていると語ります。ただし、「このビフォア・アフターで商品開発やマーケティングのやり方を変えなくてはなりませんが、日本にいると「アフターデジタル」をあまり実感しにくい」のだそうです。
アフターデジタルを体感しやすい中国の都市部で何が起きているのかを、事例を交えて紹介がありました。
モバイクの事例にみる「新しいビジネスヒエラルキー」
中国ではスマホ決済の普及が進んだため、都市部では99%のスマホ保有率となっているそうです。決済アプリのシェアではご存知の通りalipayとWeChatPayが2強で、この二つの決済プラットフォームを擁するアリババとテンセントがビッグデータを活用した新しいビジネスヒエラルキーの頂点をとっています。
中国のスタートアップは「集客」を求められる
中国で新しいサービスとして話題になったシェアサイクル「モバイク」は、15分1元ほどで利用でき、どこでも乗り捨てができるためユーザーにとっては便利なサービスです。ところが、運営コストがかかるため事業者側は赤字が続いているといいます。
事業としては赤字続きであっても、テンセントは投資を続けて事業が継続しています。その理由として、宮坂氏は2つの理由を挙げています。
- 自社の決済プラットフォームに便利なサービスを連携しておきたい
- 個人IDに紐づいた膨大な移動データを得られる
「決済プラットフォーム上で様々なサービスを連携しているため、自社が持っている決済情報や生活情報に移動データを加えて、新しいサービスやマネタイズ方法を開発できること」がテンセントの狙いなのです。
日本では投資家から求められるのは事業の収益化ですが、中国のスタートアップ企業はユーザー獲得を求められるといいます。
宮坂氏は「このように、業界の中での力関係が変化し、決済プラットフォーマーのアリババとテンセントにあらゆるデータが集まっているのが今の中国である」と語りました。
メーカーが今後パワーバランスを保つには
前項で紹介したモバイクや、配車サービスの滴滴(ディディ)、保険会社の平安(ピンアン)といったサービス提供企業の下に、これまで強いと言われていたメーカーが位置することになりました。
宮坂氏はモバイクを再度例にとり、メーカーの立場を解説します。
「シェアサイクルの普及により、商品としての自転車が買われなくなると、自転車製造工場は売上が落ちていきます。ここでモバイクが大量にシェアサイクルの発注をして、モバイクの仕様の自転車を大量生産する下請け工場になってしまったのです」
日本でもこの現象は起きるだろうと宮坂氏は予測しています。メーカーでありつつもサービサーになるか、唯一無二の製品を作るメーカーになるしかないということです。

これからの企業に重要なOMOの考え方
「O2Oの概念を進化させ、オンラインとオフラインを一体のものと捉えるOMO(Online Merges with Offline)の概念を重要視していくこと」がこれからの日本企業には必要であると宮坂氏は言います。
お客様の状況を把握したり、ターゲティングしたりといったデジタルだからこそできていたことが、リアルでもできるようになってきています。
OMOの定義について
「OMO」は2017年頃、元Googleの中国トップを務めた李開復(リ カイフ)によって提唱された概念で「Online Merges with Offline=オンラインとオフラインの融合」と訳され、オンラインとオフラインを一体として考えることとされています。
また、それより少し前の2016年にアリババのジャック・マーが提唱した「ニューリテール」もオンライン、オフライン、そして物流を融合してより優れた顧客体験を提供する、という考え方で、新しい小売の形を表現したものです。
OMO、ニューリテールともに中国から発信された概念で、既にデジタライゼーションが社会的に進んでいるからこそ生まれたとも考えられます。
その事例として取り上げられたのが保険サービスを提供する「平安(ピンアン)」です。
伝統的な保険会社がOMOで飛躍
もともと一般的な保険会社だった平安は、デジタルサービスで日常生活を支える企業として、現在時価総額23兆円と超巨大金融機関になっています。
中国では病院で受診するにも何日も待たなければならなかったり、いわゆる藪医者にひっかかってしまったりと、医療を受ける環境が良くないという背景がありました。
そこで平安が提供する「平安グッドドクターアプリ」は信頼のおける医師に気軽にチャットで相談でき、アプリから受診予約もできることが人気になっているそうです。アプリを日常的に利用することでポイントが貯まり、アプリのサービスを受けることもできます。
また、平安の保険担当者が保険の営業もかねて丁寧にフォローするため、信頼度がアップ。
日常にデジタルサービスがしっかりとマッチした結果、顧客満足度が向上し、顧客ロイヤルティが上がったというわけです。
バリューチェーンからバリュージャーニーへ
これまで、多くの企業はプロダクト中心に事業を展開してきました。バリューチェーンを形成し、マス広告を打つマーケティング手法です。
しかし、これからはカスタマーエクスペリエンス中心で考え、バリュージャーニーを作っていかなくてはなりません。
ユーザーの状況把握で生活に寄り添う
アフターデジタルの世界では属性把握ではなく「ユーザーの状況把握をし、その状況に対してうまくアプローチできているか。お客様の生活に寄り添うにはデジタルを使って状況把握を」と宮坂氏は訴えます。
ビフォアデジタルの世界では、属性はなんとなく把握できてもオフラインでの状況を把握するのは技術的に難しいことでした。
しかし、アフターデジタルの世界では「理論上は可能になる」のです。
前述の「平安グッドドクターアプリ」では、医師とのチャットのデータから「今このユーザーがどんな症状を抱えていて、どんな診断が出たのか」といった状況を把握し、保険営業担当者がユーザーに対して保険商品のアドバイスをするなど、既に実現しているサービスもありますね。
「いかに状況ターゲティングをするか、マーケティングで定着させられるかが大事」と宮坂氏は捉えています。

あるべきDX(デジタルトランスフォーメーション)の姿
「理想の顧客体験を起点とし、デジタルサービスを設計、最後にモノや場所を提供することがこれからのあるべきDX(デジタルトランスフォーメーション)の姿です」と語る宮坂氏。
これはコメ兵の藤原氏をはじめ、OMOをテーマに発信されている事業者の方がことごとく口にされることです。
日本のDXはともすれば人材コスト削減方向に偏りがちなところ、平安では逆に営業マンを増やしているそうです。それを宮坂氏は「テックタッチからハイタッチ」と表現しました。
デジタルテクノロジーで顧客とのタッチポイントを高頻度で作り、営業担当者が顧客状況を把握した上で的確にアプローチすることで、顧客ロイヤリティを高めていくことです。
アプリで顧客に案内を送っておけば、顧客が自分で動いてくれるから人員はいらない、セルフレジを置いておけば顧客が自分で会計してくれる、そういう考え方とは一線を画しています。
OMOとは、より優れた顧客体験を提供するための概念であることを必ず念頭におき、これまでのプロダクトインの考え方を転換することが必要になってくるのでしょう。
UXデータサイクルを実行するためにはデジタル人材育成がカギ
「顧客のタッチポイントをどれだけ増やすか、状況把握のための行動データをいかに収集するか。それを分析し、UXに反映する、このループを回していく会社がOMO的に勝ち残る会社になっていく」
これはデータを集めるだけでは勝てないことを示唆しています。サービスを設計したりブラッシュアップするために、データを分析する人材が必要になってきます。
これから重要になってくるのは単なるデータサイエンティストなどのデジタル人材でなく、「アフターデジタル人材」です。顧客視点でのクリエイティビティと、コミュニケーション能力を持った人材育成が今後のカギになってくるでしょう。
シーケンス分析でユーザーの状況把握を
これまでの数値データ(集計データ)での分析では見ることができなかったユーザーの行動データを、ビービット社が提供しているサービス「USERGRAM」では、ユーザーの行動を時系列に追うことができるシーケンス分析で、状況把握をおこなうことができます。

https://www.bebit.co.jp/usergram/
AIなどのツールが分析し、人間がマーケティング施策を考える、そのサポートをする「USERGRAM」のようなツールをうまく活用して、顧客にしっかりと向き合うサービスを作り上げていくべきなのでしょう。
PR:エスキュービズムによるDX推進アプローチ